|
|
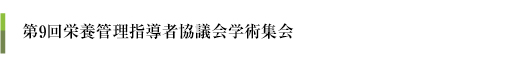
開催概要
| ○日 時: |
|
2019年3月23日(土)9:30~18:30(予定)
|
| ○会 場: |
|
星薬科大学「本館 メインホール」
|
| ○当番会長: |
|
木暮 道彦(公立藤田総合病院 外科) |
| ○テーマ: |
|
学会は「議論の場」
|
| ○プログラム:
|
|
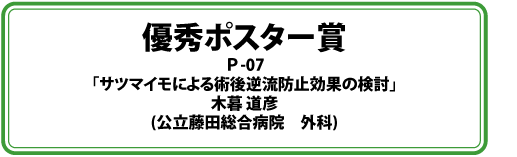
日程表
プログラム・討論テーマ
1. パネルディスカッション1
「胃食道逆流予防について、もう一度考える―経腸栄養実施時の誤嚥性肺炎防止
への対応―」
|
誤嚥防止対策はすでにいろいろ講じられていますが、うまくいった症例、うまくいかなかった症例について募集します。体位、投与方法、経腸栄養剤の選択、半固形状流動食、とろみ状流動食、粘度、などについて議論したいと思います。
|
2. パネルディスカッション2
「NST活動を本当に本音で語ろう―当院のNST:ここがダメ。どうしたらいいで
しょうか?―」
NST加算としては、専従を専任にしてもよい、ということにはなりましたが、本当にそれでいいのでしょうか。NST加算がとれるようになって、却ってNSTの活動内容のレベルが低下したのではないでしょうか。専従を専任にしてもよい、となって約1年が過ぎました。この1年の変化を、本当に本音で発表していただきたく思います。
本当に本音での発表はなかなかできないと思いますが、その壁を破ることによって真実が見えてくると思います。専従の役割って、加算をとるためだけのものだったのでしょうか。他にも重要な役割があると思うのです。この点についても、専従から専任になった方に本音で語ってもらいたいと思います。NSTをダメにしないためにも本音での発表を期待します。
|
3. 症例相談
「CKDの保存期における栄養管理―たんぱく質投与の是非を問う。われわれはこう
している―」
|
これまでに腎障害症例に対する栄養管理は、あまり演題が出てこなかったように思われます。腎疾患の栄養管理を考える際は、急性腎障害:AKI、CKDの保存期および透析期に分けて考える必要があります。特に保存期には腎機能を悪化させないための栄養管理、蛋白制限が必要ですが、栄養としての蛋白質投与も必要なため、苦労しているものと推察されます。ガイドラインには指針も載っていますが、蛋白質の投与量、方法、そのモニタリング法など、実際どのように管理されているのでしょうか?腎不全用アミノ酸を使うのでしょうか?議論できる症例を持っておられる方は積極的に出していただきたいと思います。アミノ酸、たんぱく質投与の是非、投与量はどこまでなら透析しなくて済むか、電解質等のモニタリングとの関係、うまくいった症例、いかなかった症例、について募集します。
|
4. ポスターセッション
テーマは特に設けません。積極的に応募してください。
特に、前回のテーマであまり演題が集まらなかった『栄養評価(栄養管理の有効性を評価するために)』と『静脈栄養の管理』についての演題を期待します。
もちろん、これ以外のテーマも結構です。症例報告がたくさんあると、議論しやすいと思います。
|
|
| ○事前参加登録: |
|
【事前参加登録】
期間:2019年1月25日(金)~3月1日(金) 3月8日(金)まで延長しました。
事前参加登録を終了しました。多数のご応募を頂きありがとうございました。
| 参加費: |
学術集会 |
5,000円(事前登録) |
| |
|
6,000円(当日登録) |
| |
情報交換会(懇親会) 3,000円 |
事前参加登録はこちら
|
| ○演題登録 |
|
■募集締切
2019年1月16日(水)~2月15日(金) 2月22日(金)まで延長致しました。
演題募集を締め切りました。多数のご応募を頂きありがとうございました。
■募集項目 上記4セッションで募集をいたします。
■提出方法
演題の応募は、全て電子メールにより受け付けます。
以下抄録入力フォーム(Microsoft Word (.doc) )をダウンロードの上、電子メールで送付先までお送りください。
抄録入力フォーム
1.添付のファイル名は「筆頭著者の氏名を漢字」でご記入ください。
例:「三宮 太郎.doc」
2.メールの件名は「第9回静脈経腸栄養管理指導者協議会学術集会 演題抄録」としてください。
[送付先]
第9回静脈経腸栄養管理指導者協議会学術集会 運営事務局
株式会社インターグループ内
E-mail: leaders@intergroup.co.jp
※演題の受領後、3営業日以内に受領の返信をいたします。受領返信が届かない場合には、受信が出来ていない可能性がございますので、お手数ではございますが上記送付先までご連絡ください。
■採否に関して
採否通知・採択結果はメールにてご連絡いたします。演題の採否および発表時間は事務局にご一任ください。
|
|
|
Copyright©一般社団法人静脈経腸栄養管理指導者協議会